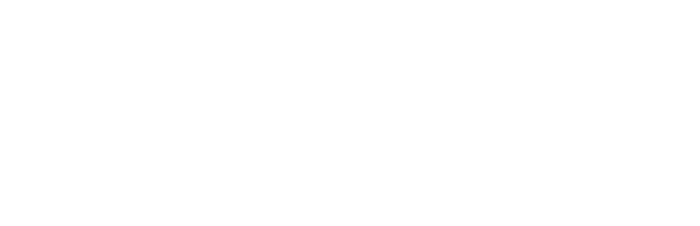施工管理資格取得ガイド:どの資格を選ぶべきか
掲載日:2025.03.09
- #施工管理資格取得ガイド:どの資格を選ぶべきか
- #施工管理の資格とは?
- #施工管理資格の種類と特徴
- #参照元
- #施工管理技士1級と2級の違いとは?
- #施工管理技士のおすすめ資格ランキング
- #施工管理資格取得のメリット
- #まとめ
施工管理資格取得ガイド:どの資格を選ぶべきか

建設業界では、施工管理の資格が、キャリアアップや収入向上の鍵となり重要です。しかし、資格ごとの特徴やメリットを知らないまま選ぶと、自分の目指すキャリアに合わない場合もあります。
この記事では、施工管理資格の種類や、選び方を初心者にも分かりやすく解説し、あなたに最適な資格を見つけるお手伝いが出来れば幸いです。あなたに適した資格取得への第一歩を、踏み出しましょう。
施工管理の資格とは?
これらの資格は、工事の品質・安全性・スケジュール管理を徹底するために必要不可欠であり、建設業法に基づく国家資格として信頼されています。
資格を取得することで、建設業界でのキャリアアップや転職が容易になり、資格手当を支給する企業も多いため、経済的なメリットもあります。
また、試験は1次検定と2次検定の2段階に分かれており、それぞれで専門知識や実務能力が問われます。施工管理の資格は、建設業界での信頼性と安定性を確保するために、取得を目指す価値のある資格です。
施工管理資格の種類と特徴
1.建築施工管理技士
2.土木施工管理技士
3.電気工事施工管理技士
4.管工事施工管理技士
5.電気通信工事施工管理技士
6.建設機械施工技士
7.造園施工管理技士
それぞれの資格が、どのような場面で役立つかを解説します。
1.建築施工管理技士
建築施工管理技士は、マンションや商業施設、オフィスビルなどの建築工事を管理する資格です。この資格を取得すると、建築プロジェクト全体を統括する現場監督としての役割を果たせます。特に1級は大規模な建築物を担当できるため、建築業界でキャリアアップを目指す方におすすめです。
仕事内容
・工事の進行スケジュールの管理
・安全管理や品質管理
・各専門業者との調整
建築現場では多くの人々が関わるため、統率力や調整力が求められる場面が多くあります。
受験資格と試験概要
2024年度から受験資格が大幅に緩和され、学歴や実務経験に制限がなくなりました。
【1級】
第一次検定は、試験実施年度末時点で19歳以上であれば誰でも受験可能です。第二次検定は第一次検定合格後、実務経験を積む必要があります。
【2級】
第一次検定は試験実施年度末時点で17歳以上で受験可能です。第二次検定は第一次検定合格後に実務経験が必要です。
実務経験の証明は、勤務先の代表者や監理技術者による証明が必要で、工事単位で記録されます。資格取得を目指す際のハードルが下がり、挑戦しやすい制度となりました。
2.土木施工管理技士
土木施工管理技士は、道路や橋、水道設備、トンネルなどのインフラ工事を管理する資格です。公共事業やインフラ整備に携わりたい方にとって重要な資格で、地域社会の基盤を支える仕事に直結します。特徴と活用シーン
・公共事業の受注に必要不可欠
・工事の計画立案から現場の進行管理まで幅広く対応
・1級取得者は大規模インフラプロジェクトを担当可能
土木工事は長期間にわたることが多く、プロジェクト全体を見渡す視野と、細部に目を配るスキルが重要です。
受験資格と試験概要
2024年度から、受験資格が学歴に関係なく受験可能となり、より挑戦しやすくなりました。
【1級】
第一次検定は満19歳以上で受験可能です。第二次検定は、一次検定合格後、特定実務経験を含む3年以上の実務経験が必要です。 【2級】
第一次検定は満17歳以上で受験可能です。第二次検定は、一次検定合格後、同じく3年以上の実務経験が必要です。
特定実務経験とは、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事における監理技術者または主任技術者としての経験を指します。1次試験は筆記中心、2次試験は実務経験を踏まえた実践的な内容が問われます。
3.電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、照明設備や送電設備、発電所関連の工事を管理する資格です。電気設備は建築物やインフラ整備に欠かせない要素であり、この資格を持つことで幅広い現場での活躍が期待されます。資格のメリット
・電気関連の大規模工事に携われる
・企業の信頼度アップに寄与
・エネルギー効率化や環境配慮型工事の需要増加に対応
特に、近年の再生可能エネルギー関連の工事が増加しており、資格保持者の需要は高まり続けています。
受験資格と試験内容
2024年度から受験資格が改訂され、受講しやすくなりました。 【1級】
第一次検定は、学歴や実務経験の制限がなくなり、試験年度末時点で19歳以上であれば受験可能です。基礎的な知識を問う筆記試験が行われますj。 第二次検定では、実務経験が必要で、施工管理に関わる計画・工程・品質・安全管理の職務経験が求められます。 【2級】
第一次検定は、試験年度に満17歳以上であれば受験可能です。第二次検定では実務経験が求められます。 1級では、2次試験合格後に「監理技術者」として、2級では「主任技術者」「専任技術者」として建設現場で活躍できます。
4.管工事施工管理技士
管工事施工管理技士は、給排水設備や空調設備、ガス配管などの工事を管理する資格です。ビルや住宅の快適さを支える設備工事において、この資格は欠かせません。主な仕事内容
・配管設計と施工計画の策定
・配管材や機器の選定・発注
・工事現場での品質管理
空調や給排水は建物の利用者に直結するため、施工精度が求められる分野です。この資格は、特定建設業の「専任技術者」「主任技術者」としての役割を担うための第一歩となります。
受験資格と試験内容
【1級】
2024年度から、第一次検定は、学歴や実務経験の制限がなくなり、試験年度末時点で19歳以上であれば受験可能です。一方、第二次検定では実務経験が必須です。
【2級】
第一次検定は、試験年度に満17歳以上であれば受験可能です。第二次検定では実務経験が求められます。
資格取得後は「管工事施工管理技士」の称号が与えられ、技術検定合格証明書が交付されます。この資格は、学歴や経験に応じて、異なる受験要件をクリアしながら取得でき、技術者としてのキャリアアップに大きく寄与します。
5.電気通信工事施工管理技士
電気通信工事施工管理技士は、インターネット回線や携帯基地局、LAN工事など通信インフラを整備するための資格です。現代の情報化社会において、ますます需要が高まっています。活躍の場
・新規通信設備の設置
・基地局やデータセンターの建設
・通信障害や電波調査への対応
この資格を持つことで、5Gや次世代通信網の整備といった最先端の技術分野に関わるチャンスが広がります。
受験資格と試験概要
令和6年4月1日以降、電気通信工事施工管理技士の受験資格が大幅に緩和されました。 【1級】
受験資格は、19歳以上で受験可能です。第一次検定に合格後、第二次検定を受験できます。
【2級】
受験資格は、17歳以上で受験可能です。第一次検定に合格し、所定の実務経験を積むと第二次検定を受験可能になります。
実務経験は、電気通信工事に直接携わる技術的な業務が対象となります。試験は、第一次が学科中心、第二次が実務能力を評価する構成です。
6.建設機械施工技士
建設機械施工技士は、重機を使った工事に関する資格です。特にダンプトラックやブルドーザーなど、専門性の高い機械の操作や管理に携わります。仕事内容の例
・重機を用いた土砂の移動や整地
・工事現場の安全管理
・工程やコストの調整
この資格を取得することで、大規模な土木工事や造成工事で重要な役割を果たすことができます。
受験資格と試験の概要
建設機械施工管理技士には1級と2級があり、それぞれ受験資格が異なります。
【1級】
2級取得後5年以上の実務経験が必要です。また、学歴に応じた実務経験や、専任の主任技術者として1年以上の経験を含む場合は3年以上で受験可能です。 【2級】
2024年4月からは、第一次検定で学歴や実務経験が不要となり、受験しやすくなりました。第一次検定を満17歳以上で受験できます。
第二次検定は第一次合格または、一定の実務経験で受験資格を得られます。試験の違いとして、第一次検定は基礎知識を問う筆記試験、第二次検定は実務に基づく判断力や応用力を問います。経験を活かした準備が重要です。
7.造園施工管理技士
造園施工管理技士は、公園や庭園、遊歩道などの緑地整備に必要な資格です。自然環境との調和を図る仕事で、環境保護や地域美化の観点からも重要視されています。求められるスキル
・緑地計画や設計の知識
・造園工事の進行管理
・地域の気候や生態系を考慮した提案力
この資格は、自治体や民間企業の緑化プロジェクトで活躍する機会を提供します。これらの施工管理資格は、それぞれ特化した分野で必要とされるスキルを証明するものです。
受験資格と試験概要
2024年度から受験資格が拡大され、第一次検定(学科試験)は学歴や実務経験に関係なく受験可能となりました。一方で、第二次検定(実務試験)には実務経験が必須です。
【1級】
第一次検定は、19歳以上で受験可能です。第二次検定は、第一次検定合格後、特定実務経験を含む1〜5年の実務経験が必要になります。
【2級】
第一次検定は、17歳以上で受験可能です。第二次検定は、第一次検定合格後、3年以上の実務経験が必要になります。
資格選びのポイント
自分が興味を持つ分野や、将来的に携わりたいプロジェクトに焦点を当てることが肝要になります。・建築分野を目指す:建築施工管理技士
・インフラ整備に興味がある:土木施工管理技士
・エネルギー関連を重視する:電気工事施工管理技士
・通信インフラの未来に携わりたい:電気通信工事施工管理技士
資格はまず2級を取得し、経験を積んで1級を目指すことでステップアップが可能です。適切な資格選びを通じて、建設業界でのキャリアアップを実現しましょう。
参照元
施工管理技士1級と2級の違いとは?
1級は主任技術者や監理技術者として、大規模かつ複雑なプロジェクトを統括できます。一方、2級は主に小規模から中規模の現場で主任技術者として活躍し、特定の分野に特化した業務を担当するケースが多いです。
例えば、建築施工管理技士の場合、1級は建築全般における監理技術者として現場全体を統括可能です。一方、2級では建築・躯体・仕上げといった特定の分野に分かれており、その分野内で主任技術者として活躍します。
同様に、土木や管工事でも1級の方が業務範囲が広く、管理責任が高い役割を担います。
施工管理技士1級の取得メリット
1級施工管理技士の取得は、キャリアアップと収入向上に直結します。 主任技術者だけでなく、監理技術者としての業務が可能になるため、大規模プロジェクトや公共工事で活躍する機会が広がります。また、企業にとっても1級取得者の存在は、入札や経営事項審査の加点に繋がるため、採用や待遇面で優遇されるケースが多いです。 このように、1級資格を取得すると、次のようなメリットがあります。
・管理技術者として大規模な現場を担当できる
・経営事項審査で加点が得られる
・業界内での信頼性と評価が向上する
・収入面での優遇や昇進の機会が増える
これらの理由から、長期的なキャリア形成を考える際には1級取得が大きな武器となります。
施工管理技士2級の取得のしやすさ
2級施工管理技士は、初心者や若手技術者が第一歩として挑戦しやすい資格です。 必要な実務経験年数が1級よりも短く、試験内容も比較的基礎的な範囲が中心となっています。また、建築・土木・管工事など特定分野に絞って学べるため、特化した知識を身につけやすい点も特徴です。
2級資格取得の主なメリットとして、以下が挙げられます。
・早期に現場で活躍できる技術者になる
・特定分野に特化したスキルを証明できる
・試験内容が1級よりも学びやすい
2級の取得は、実務経験を積みながら1級取得を目指すステップアップの基盤としても活用できます。
このように、施工管理技士の1級と2級は、それぞれの役割や適性に応じて異なる価値を持ちます。1級は大規模現場を統括し、収入やキャリアアップに直結する資格であり、2級は基礎を固める最初のステップとして最適です。
自分の目指すキャリアパスに合わせて資格を選択し、スキルアップを図りましょう。
施工管理技士のおすすめ資格ランキング
ただし、資格ごとに難易度や求められるスキルが異なるため、自分に合った資格を選ぶことが重要です。
ここでは、初心者でも取得しやすい資格をランキング形式で紹介し、それぞれの特徴や学習方法を詳しく解説します。
初心者におすすめの資格3選
1.2級土木施工管理技士2.2級建築施工管理技士
3.1級土木施工管理技士
1.2級土木施工管理技士
初心者に最もおすすめなのが「2級土木施工管理技士」です。この資格は、土木工事に関する基本的な知識や技能を問うもので、建設業界への第一歩として適しています。試験の特徴
学科試験と実地試験があり、学科試験は比較的取り組みやすい内容となっています。
合格率
学科試験の合格率は43%で、実地試験の合格率も44.6%前後と安定しています。
ポイント
独学でも十分に合格を目指せる試験ですが、学習計画を立てて着実に進めることが重要です。
2.2級建築施工管理技士
建築分野で活躍を目指す方におすすめです。この資格は、建築工事の施工管理に関する基礎的な知識を問うもので、初学者にも取り組みやすい内容となっています。試験の特徴
土木施工管理技士と同様に学科試験と実地試験があり、実務経験が短くても受験できるのが魅力です。
合格率
学科試験の合格率は50%前後で、実地試験も同程度の水準です。
ポイント
初めて施工管理技士を目指す場合は、2級建築施工管理技士から挑戦するのが効果的です。
3.1級土木施工管理技士
難易度は上がりますが、土木分野でのキャリアアップを目指す方には「1級土木施工管理技士」が最適です。2級資格取得後に挑戦することで、さらに高い専門性を身につけられます。試験の特徴
試験内容は専門性が高くなり、一次試験(学科)と二次試験(実地)の両方をクリアする必要があります。
合格率
2級の合格率は50%〜60%程度、1級の合格率は30%〜40%程度と、合格率の差はそこまで大きくはありません。より専門的な知識を問われるため、難易度は上がっています。
ポイント
実務経験が求められるため、現場での経験を活かした学習が重要です。
資格取得のための学習方法
施工管理技士の資格を取得するには、しっかりとした学習計画と効果的な学習方法が欠かせません。以下、初心者でも取り組みやすい学習方法を紹介します。
過去問題の徹底分析
過去問題は試験の傾向を知るための最良の教材です。繰り返し解くことで、出題パターンや頻出分野を把握できます。
参考書や問題集の活用
市販の参考書や問題集を選び、基礎から応用まで幅広く学習しましょう。特に初学者向けの分かりやすい解説がある教材を選ぶと効果的です。
オンライン講座の利用
最近では、オンライン講座が充実しており、動画で分かりやすく解説してくれるものも多くあります。通勤や休憩時間など、隙間時間を活用して学習できる点が魅力です。
学習計画の作成
資格取得には計画的な学習が不可欠です。目標とする試験日に向けて週単位や月単位で学習スケジュールを作成し、無理のないペースで進めましょう。
模擬試験で実力を確認
模擬試験を受けることで、自分の弱点や苦手分野を把握できます。試験直前には、実際の試験と同じ時間配分で練習すると、時間管理の感覚も養えます。
施工管理技士の資格取得は、建設業界でのキャリア形成に大きく貢献します。まずは初心者向けの資格から挑戦し、実務経験を積みながら次のステップを目指しましょう。適切な学習方法と継続的な努力が、合格への最短ルートです。
施工管理資格取得のメリット
昇給・昇進につながる
施工管理技士の資格を取得すると、給与アップが期待できます。多くの企業では資格手当が支給されるため、毎月の給与に加算されるほか、昇進の条件として資格取得を求めるケースもあります。資格手当は月額5,000円から1万円程度、一時金として10万円程度支給されることもあり、長期的な収入増加につながります。「監理技術者」「主任技術者」になれる
建設現場で「監理技術者」や「主任技術者」として働くためには、施工管理技士の資格が必要です。監理技術者:
1級施工管理技士が対象。高額工事や大規模プロジェクトで必須。
主任技術者:
2級施工管理技士が対象。小規模から中規模の工事で必要。
これらの役割は、現場の指揮をとり、工程や品質を管理する重要なポジションです。
「専任の技術者」として活躍できる
一般建設業や特定建設業の営業許可を得る際に、「専任の技術者」の配置が必要です。1級または2級施工管理技士を保有していることで、建設業界での信頼性が高まり、より多くのプロジェクトに参画できる可能性が広がります。経営事項審査の加点対象になる
公共工事を受注する企業は、経営事項審査(経審)を通過する必要があります。この審査では、資格を持つ技術者の人数が評価され、1級施工管理技士は5点、2級は2点の加点対象となります。このため、資格取得は企業の競争力向上に直結します。幅広いキャリアパスが得られる
施工管理技士の資格を取得すると、転職市場での評価が高まります。資格保持者は、多様な工事現場での経験を積み、スキルを磨くことで、次のようなキャリアパスを描けます。・大規模プロジェクトの管理者
・建設コンサルタントへの転身
・独立開業しての施工管理業務
施工管理資格は、建設業界での活躍を目指す方にとって非常に有益な資格です。給与や昇進のチャンスを広げるだけでなく、現場での信頼性を向上させ、転職やキャリアアップにも役立ちます。自分に適した資格を選び、将来に向けた準備を進めましょう。
まとめ
初心者はまず2級資格から挑戦し、実務経験を積みながら1級を目指すのがおすすめです。適切な資格を選び、計画的に学習することで、長期的なキャリアアップの土台を築けます。
また、公共工事をはじめとする大規模プロジェクトへの参画や、独立開業といった幅広い選択肢を得られるのも大きな魅力です。施工管理資格を活用し、自分の目指すキャリアに向けて大きな一歩を踏み出しましょう。
お仕事別おすすめ転職サイト